「台風のたまごが発生しました」──そんなニュースやSNSの投稿を目にすること、増えてきましたよね。
でも実は、「台風のたまご」という言葉は気象庁が公式に使っている用語ではありません。
この記事では、「台風のたまご」ってそもそも何?という基本から、どういう条件で発生し、どのように台風に発展するのか、そして米軍JTWCや気象庁、ヨーロッパECMWFといった各気象機関の予測の違いまで、わかりやすく解説していきます!
台風のたまごとは?意味をシンプルに解説
「台風のたまご」とは、簡単にいえば「台風になりそうな熱帯低気圧(または熱帯擾乱)」のこと。
テレビやネットの気象解説、SNSなどでは広く使われている通称ですが、正式な気象用語ではありません。
たとえば、米軍の合同台風警報センター(JTWC)が熱帯擾乱に「Invest 97W」などの番号を付けて監視を始めると、多くの気象ウォッチャーが「これは台風のたまご」と注目しはじめます。
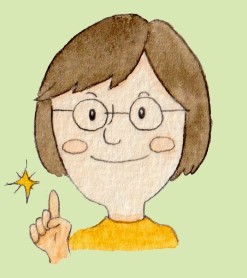
「たまご=台風の前段階」というイメージで覚えるとわかりやすいよ!
\備えあれば憂いなし/
台風のたまごが発生する条件は?
台風のたまご(熱帯擾乱・熱帯低気圧)は、以下のような条件が揃うと発生しやすくなります。
- 海面水温が約26.5℃以上と高い
- 大気の状態が不安定(上昇気流が起こりやすい)
- 弱い風の渦(擾乱)がある
- 高度によって風向が大きく変わらない(垂直シアが小さい)
とくにフィリピンの東海上やマーシャル諸島周辺は、これらの条件が揃いやすく、台風のたまごの発生源となりやすいエリアとして知られています。
\備えあれば憂いなし/
たまごの段階で発表される情報とは?
台風のたまごは「まだ台風ではない段階」なので、日本の気象庁では正式な台風情報が出ることはほとんどありません。
一方、早くから注視しているのが米軍JTWC(合同台風警報センター)。
JTWCでは熱帯擾乱に「Invest XXW(例:97W)」といった番号をつけ、進路や発達の予測を出しています。これが、私たちが「たまご」と呼ぶきっかけになることが多いです。
さらに、ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)やアメリカのGFSモデルなども、この段階から数値予報で動きを予測しています。
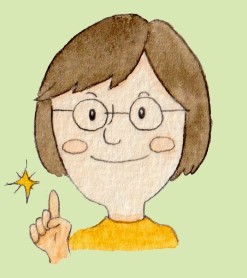
JTWCやECMWFの予測モデルは、
台風前からかなり頼りになるよ!
\備えあれば憂いなし/
たまごから台風になるまでの流れ
では、台風のたまごが実際に「台風」になるには、どんなステップがあるのでしょうか?
- 海上に雲が集まり、低気圧性の渦(熱帯擾乱)ができる
- 風速が徐々に強まり、気象機関が熱帯低気圧として監視を始める
- 最大風速が17.2m/s(約34ノット)以上になった段階で「台風」に昇格
- 気象庁が「台風○号」と命名し、台風情報を発表
つまり「たまご」は、まだ風速が弱く、台風の基準に満たない段階というわけです。
\備えあれば憂いなし/
JTWC・気象庁・ECMWFの違いを知っておこう
台風のたまごを監視する上で、よく出てくる3つの機関の特徴を簡単にまとめてみます。
| 機関名 | 主な役割 | たまごへの対応 |
|---|---|---|
| JTWC(米軍) | アメリカ海軍・空軍による熱帯低気圧監視 | “Invest”番号をつけて早期から注視 |
| 気象庁(日本) | 日本国内の気象監視と台風命名 | 熱帯低気圧→台風になってから発表 |
| ECMWF(ヨーロッパ) | 世界有数の高精度数値モデルを提供 | アンサンブル予測で先を読む |
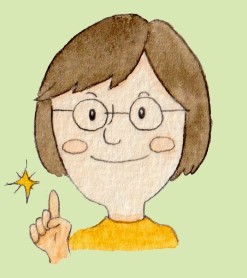
たまご段階でも各機関の予測を比較すると、
信頼度がグッと上がるよ!
\備えあれば憂いなし/
よくある疑問Q&A
Q. 台風のたまごって誰が決めてるの?
→ 正式な定義はありませんが、多くの場合、JTWCが「Invest」番号をつけた段階で「たまご」として扱われることが多いです。
Q. たまごの段階でも注意報は出る?
→ たまごだけでは注意報は出ませんが、雨雲の発達や局地的な大雨の可能性はあります。
Q. たまごが必ず台風になる?
→ いいえ。半分以上は発達せずに消滅することも多いです。
\備えあれば憂いなし/
まとめ:台風のたまごを見つけたら、こまめに情報チェック!
「台風のたまご」は、まだ正式な台風ではありませんが、気象予測の“第一歩”として非常に重要な存在です。
JTWCやECMWFなどの予測モデルを早めにチェックしておくことで、旅行やイベント、農作業などの計画にも備えができます。
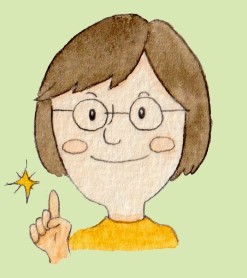
台風は突然来るわけじゃない!
たまごの段階から備えておくのがポイントだよ!
\備えあれば憂いなし/
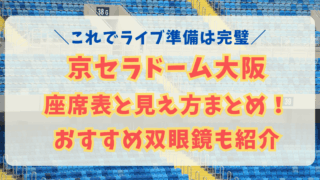
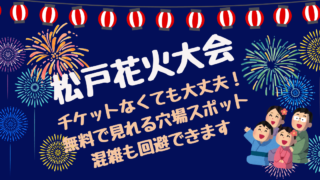
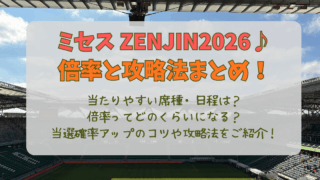
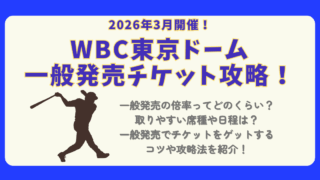

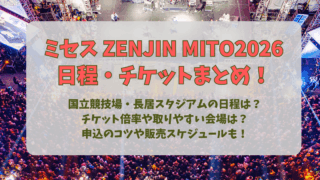
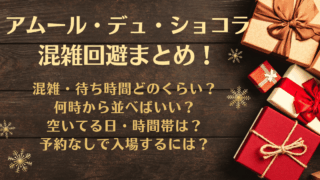
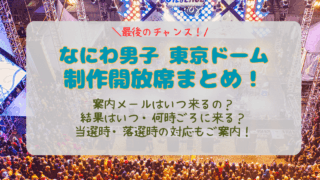
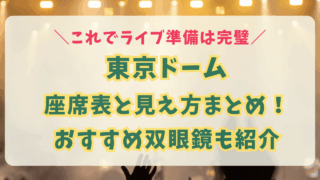
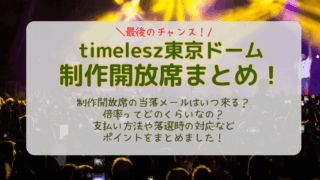
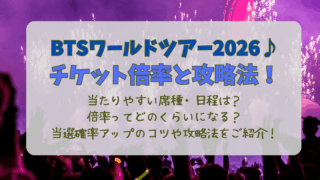
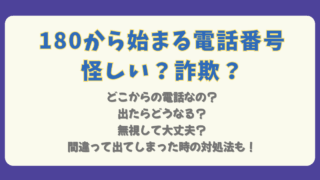

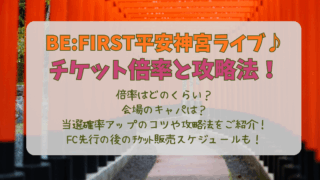
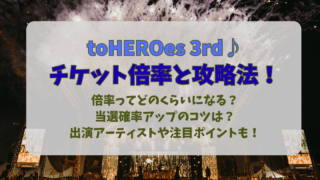
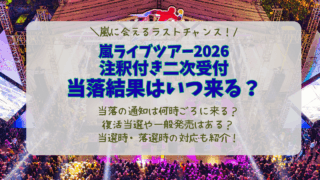
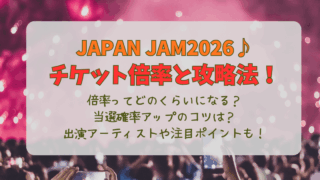
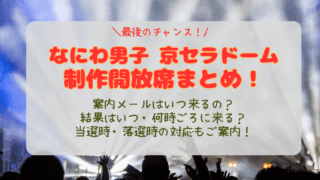






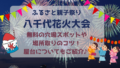

コメント